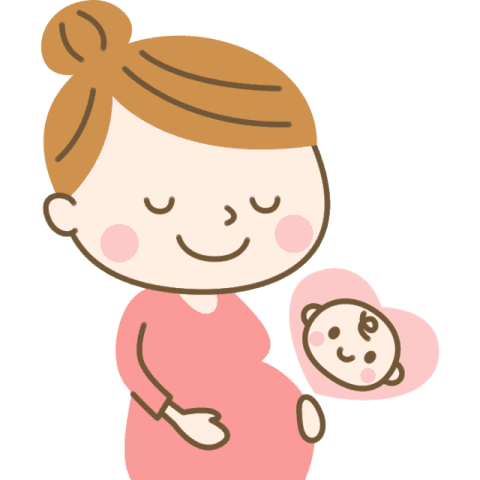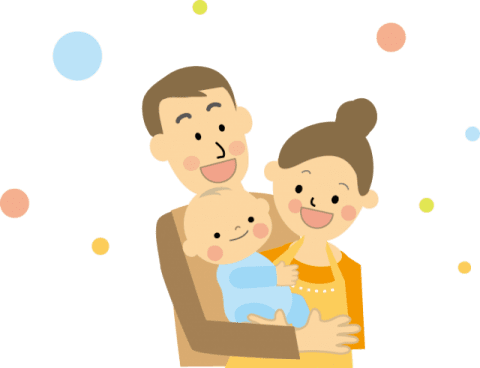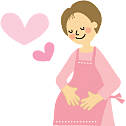不妊相談
元気な赤ちゃんの元気なママになるために
『赤ちゃんがほしい』と思っているのに、なかなか授からない。
『何をしていいのか?病院に行くのに抵抗がある。』
『病院の不妊治療で、ストレスを感じている。』
不妊に関して、いろいろなお悩みで辛い思いをされている方が、多くなっています。
病院での不妊治療は、驚くほど進み、治療の選択肢が増えたかのようですが、
思うようにいかない方も、実際には多くいらっしゃいます。
私は、妊娠、出産、育児、その中でのいろいろなトラブル、、、を経験した1人として
妊娠すればいいのではなく、
元気な赤ちゃんが生まれ、ママが元気に子育てできることが
大切だと思っています。
不妊相談って、誰にすればいいのかな? 家族にも言いづらいし
話を聞いてもらえるだけでもいいんだけど、、、
そんなお悩みを抱えていらっしゃる方の
ちょっとだけ、ホッとできる場所になれたらいいな!っと思っています。
ご相談ご希望の方は、お電話でご予約くださいね。
TEL058-275-3132
岩井 久実子
妊娠について知りましょう!
不妊治療をする前に、
不妊の原因や治療についてよく知ることが大切です。
そして、1番大事なことは、
自分達の体についてよく知り
ご夫婦が理解、協力することです

病院ではできない、不妊治療に必要なこと
当店オリジナル不妊治療
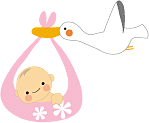
* 胃腸の汚れ取り
* 子宮・下半身の血流改善
* よい卵作り・よい子宮作り
* 陰陽バランス (周期療法)
病院の不妊治療では、なかなかできない部分で、
治療にもプラスとなることをするために
食事をはじめとした、生活習慣の改善のアドバイスをさせていただきます。
体にやさしい、漢方薬や自然薬、必要な栄養(サプリメント)により
元気な赤ちゃん作りをしましょう。
妊娠中、もう子育ては始まっているよ!
妊娠中から始まるママの役目
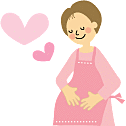
お母さんのお腹にいる赤ちゃんは、お母さんが
食べたものからしかできません。
添加物の多い食品(加工食品・コンビニ弁当)、
糖分の多いもの
体を冷やす冷たいものは、控えましょう。
お母さんのお腹にいる赤ちゃんはお母さんのストレスを敏感に感じています。
特に妊娠初期、脳や神経を形成する時期のストレスは、子供の情緒と関わってくると言われます。
元気な赤ちゃんの誕生のために、おだやかに妊娠生活を送るために、
いつでも相談してくださいね。
頑張るママの応援団
一人で悩まず、笑顔で子育てできるように!

妊娠中・産後のお母さんの体のケアは、
元気に育児をする上で、とても大切です。
特に、産後21日間は、
解毒し、元の体に戻るために大切な時!!
この時期の過ごし方や、栄養の摂り方で産後うつの予防もできるのです。
実家に戻らず出産される方や、核家族が増え、初めての育児は心配でいっぱいなのに誰にも相談できず、頑張っているママさん!
おっぱいが出ない。 夜泣きがひどい。 急な熱。 皮膚が赤くなった。
ワクチンはどうすればいいの? 気軽にお話に来てくださいね。
アレルギーの少ない、心の安定した子育てには、
おっぱいをあげるお母さんの食事、離乳食の進め方がとても大切です。
お母さんが、お子さんに伝える食育も一緒に勉強しましょう!!
お客様の声
これが最後と思って、、、

病院での不妊治療をしても、なかなかできず、ホルモン剤のせいで、体調が悪くなったりしていました。
妊娠しやすい体作りをする為に、知人から薬局を紹介されました。
元気な赤ちゃんとママになるためにと、漢方と栄養を飲みました。
40歳を過ぎての妊娠だったので、いろいろ心配だったけど、肌のきれいな元気な息子を無事に出産。
出産後の産後ケアや、赤ちゃんの離乳食のことも相談できて、息子は、薬局に行くのが大好きです。
腹痛が心配で、、、
夫婦で相談

漢方の相談をするのが初めてで、何を聞いたらいいのか?
何を勧められるのか?不安だったけど、私が聞きたいこと、主人が聞きたいことがそれぞれ違っても納得いくまで説明してくれた。
夫婦で楽しく話に行けるお店なので、とてもよかった。